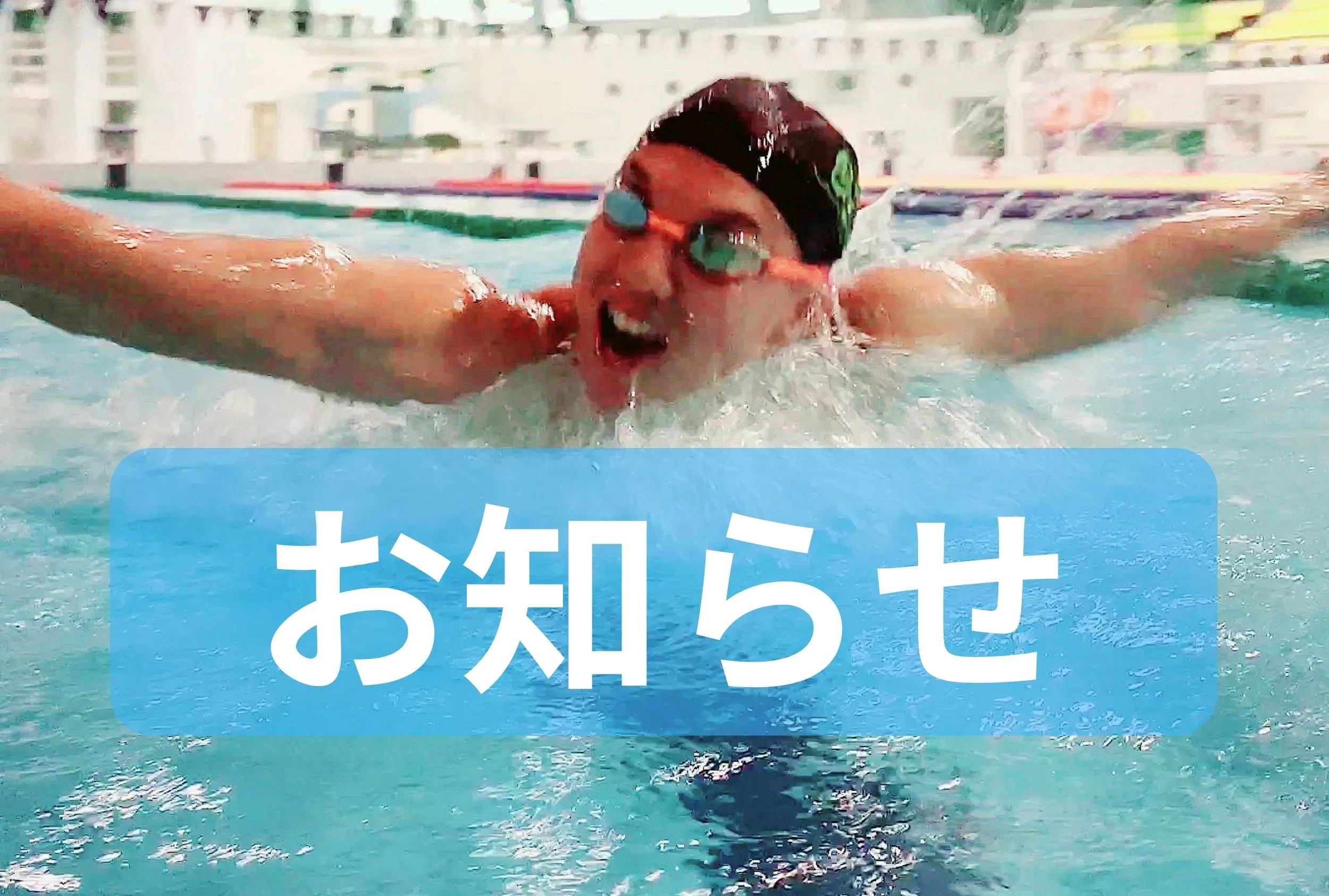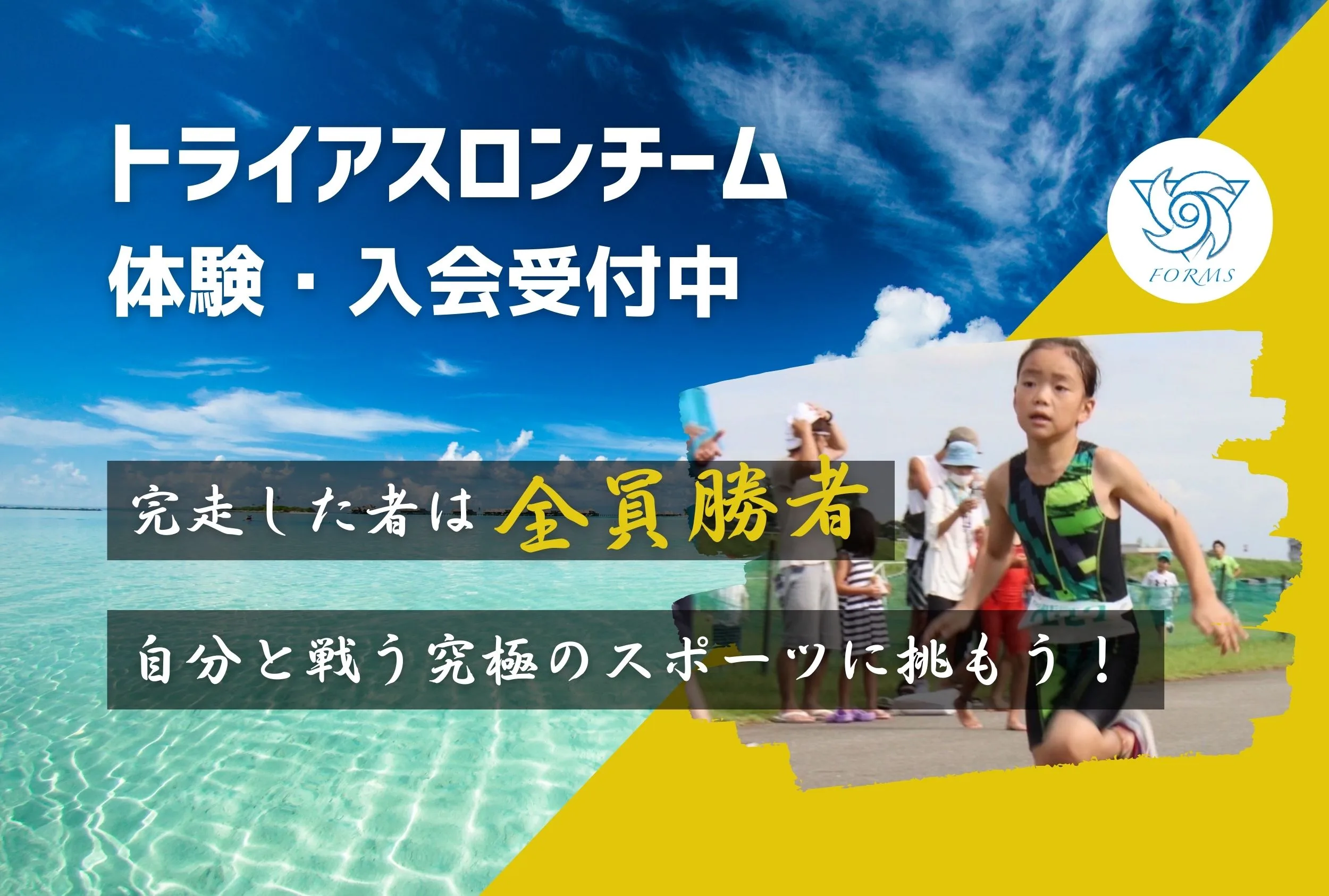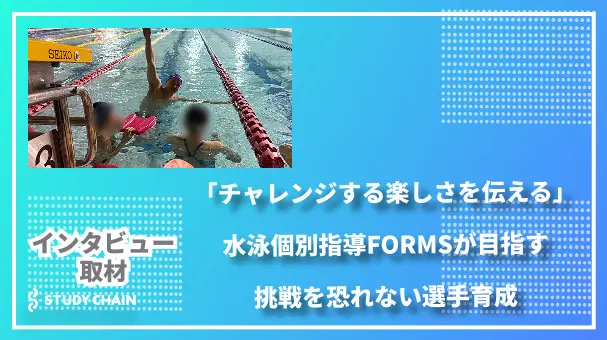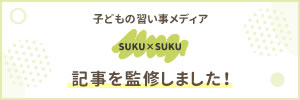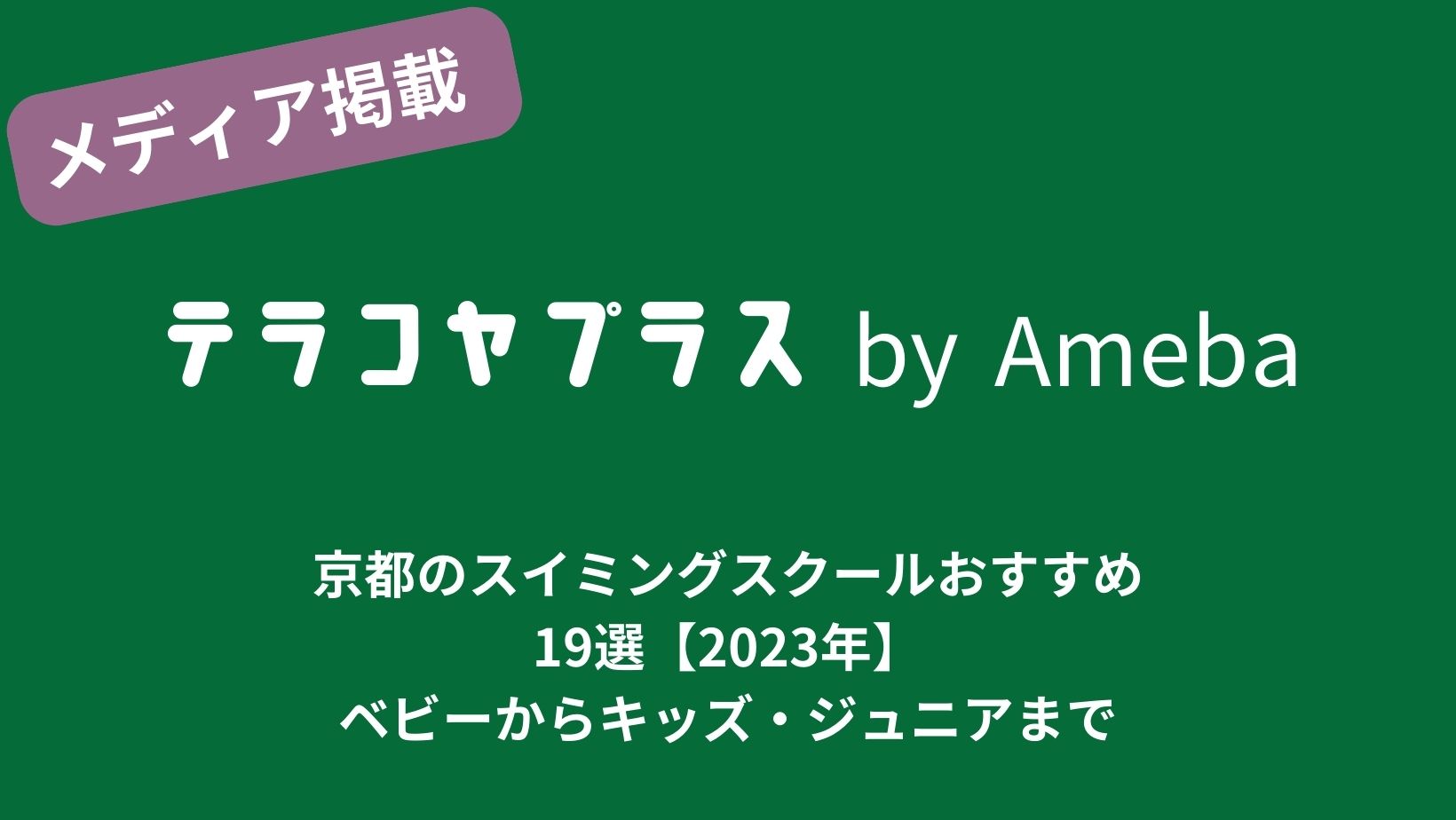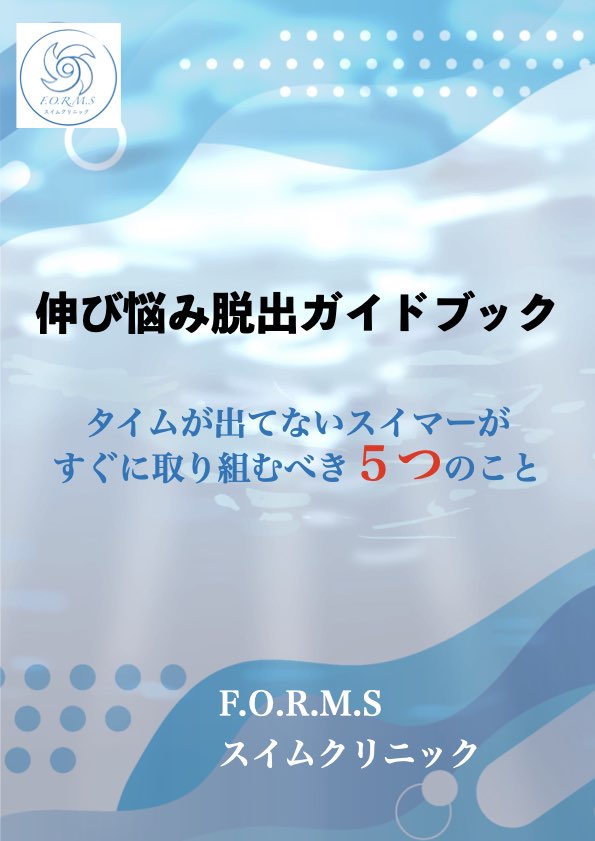泳ぐときに受ける水の抵抗とは3つの抵抗を合わせたものです。①粘性抵抗、②造波抵抗、③圧力抵抗です。1つずつ解説していきます。水の抵抗を減らすことで、余計な力を使わずに泳ぐことができます。また、泳ぐ速度が上がるにつれ水の抵抗は増加するので、上級者になるほどにさらに高い技術で泳ぐことが求められます。
趣味でも競泳でも、マスターズでも水泳をする人たちにとっての大きな関心の1つが泳ぎの中で水の抵抗を減らすことだと思います。
では、皆さんは
水の抵抗とは何?
と問われた時に具体的に答えることができるでしょうか?今回は泳ぎの中で私たちに影響を与える水の抵抗の種類についてご紹介し、泳ぎを改善していくヒントを示せたら良いなと思います。
こんな情報、ネットでは初めてじゃないかな?(書いてる現時点では)
ちなみに神回です。

難しいところもあるけど、注釈を入れるので、ぜひ読んでみてください!
いざ行かん!
目次
泳ぐときの水の抵抗①:粘性抵抗
まず1つは粘性抵抗(摩擦抵抗)です。
粘性抵抗は水の中を移動する体の表面とプールの水の粘性力から生まれる抵抗です。
粘性抵抗が大きいほど、体の後ろに引きづられる水の量が増え、前に進む邪魔も大きくなります。
粘性抵抗:
例えば、泥沼に脚を入れた時って、泥がまとわりついて動きにくいですよね。

泥の中で脚を速く動かそうとするとさらに重い!!
プールの水よりも泥沼は粘性抵抗が大きいこと、速度に比例して抵抗が大きくなることがわかると思います。
粘性抵抗は泳ぐスピードに比例して大きくなりますが、比較的わずかな増加なので後で紹介する2つの抵抗ほどには大きな影響を受けません。
粘性抵抗を減らす努力としては、水と体が接する面積を減らすこと、体の表面をつるつるにすることです。
水と体が接する面積を小さくするには、できるだけ高いボディポジションで泳ぐことで水と接する面積が減ります。
ただし、後で述べる造波抵抗との兼ね合いもありますので一概には言えません。
体の表面をつるつるにする(撥水性を高めて摩擦抵抗を減らす)のは、シリコンキャップの着用・レース水着の着用が一般的です。
レース前に全身の毛を剃るスイマーがいますが、これも一定の効果はあると考えられます。

泳ぐときの水の抵抗②:造波抵抗
造波抵抗は前に進むために押しのけた水によって生まれる抵抗です。
泳いで前に進むことで体の前側には水が重なっていきます、一方で体の後ろ側は水の量が少なくなります。
そうすると波ができて抵抗になります。
泳ぐスピードが上がるにつれ、造波抵抗も大きくなります。

泳ぐスピードの上昇によって最も影響を受けやすいのが造波抵抗で、泳ぐ速度の3乗に比例すると言われています。
粘性抵抗は比例、圧力抵抗は2乗に比例なので、最も付き合い方を考えるべきは造波抵抗かもしれません。
【オリンピック選手って実はすごい抵抗を受けている?!】
スピードが上がれば上がるほど抵抗が大きくなるので、実はそう。
最大限削れる姿勢だけど、それでも抵抗がすごいです。

特に短距離選手は抵抗が大きくなりやすいので、速いピッチで水流をの邪魔にならないように腕を回し、抵抗があっても打ち勝つパワーが必要です!
造波抵抗は水面にいる時よりも水中にいるときの方が小さくなります。
水中にいる時は空気の層と水の層の境目から離れるため、波の影響を受けないからです。
ドルフィンキックやバサロキックが得意な選手が15mギリギリまで水中を潜って進むのは、造波抵抗とキックで生み出せる推進力を比べた時に、その方が速度が出やすいからです。
一方、ドルフィンキックが苦手な人が15mギリギリまで潜っていても、造波抵抗こそ減りますが、推進力を生む効率も悪くなるので早く浮き上がってきて大きな推進力を生むストロークをした方がレースで有利になります。

造波抵抗が減るからといって、潜ったり浮いたりと上下動の多い泳ぎ(大きすぎるうねりのバタフライ)をすると、それはそれで抵抗を受ける面積が大きくなり、推進力も生みにくくなるので効率が悪くなります。
他にも、泳ぐことでできた波が自分のレーンの前方の壁に当たるので、抵抗を受けにくいようにターンをする技術を身に付ける練習が必要です。
もちろんスピードが上がるにつれ大きな波ができますので、ターン練習をする際にはゆっくり泳いで動きを確認するだけでなく、レーススピードで行うことも効果的です。
ターンのコツに関しての記事はこちら!
泳ぐときの水の抵抗③:圧力抵抗
最後は圧力抵抗です。
圧力抵抗は、体の前側と後ろ側で水にかかる圧力差から生じます。
前に進んでいく=前の水を押すことになるので前側の圧力が高くなります。
水は圧力の高い前側(頭側)から低い後ろ側(脚側)へ流れていきます。
流れていった水はある地点で体から離れていき、渦ができます。
前側の圧力と後ろ側の圧力差が大きいほど圧力抵抗は大きくなります。
渦ができる地点が後ろなほど、圧力差は小さいです。
【なんでけのび練習が大切なのか??】
例えば、水泳の基本であるけのび(ストリームライン姿勢)で頭が上がって下半身が沈んでいると、前側で水が体にぶつかる面積が大きくなり、前側の圧力が大きくなります。
さらに、頭が上がっていることで頭の付近に乱流ができ、水の流れを邪魔します。

そうすると、頭の後ろから足先にかけて渦ができてしまい、前側と後ろ側の圧力差も大きくなり、圧力抵抗が大きくなります。

一方、頭をしまって体が一直線になる綺麗な流線型のストリームラインを取れていれば、水が手先から足先まで邪魔なくスーッと流れていき、乱流は後ろの方でできます。
前側と後ろ側の圧力差が小さくなり、圧力抵抗も小さくなります。
各泳ぎのシーンでも、頭(アゴ)が上がりがちであったり、下半身が沈んで体の角度が大きかったりすると同様の現象が起こり、抵抗の大きな泳ぎになります。
胴体~肩幅から大きくはみ出しすぎないキックを打つこと、呼吸動作を行うこと、体の角度が大きくならないことを心がけて泳ぐことで圧力抵抗は減らすことができます。
できますが、そのフォームで推進力が小さくなるとそれはそれで進まなくなるので、自分にあったフォームを探す試行錯誤が必要です。
圧力抵抗も粘性抵抗や造波抵抗と同様に泳ぎのスピードが上がるにつれ増加します。
圧力抵抗は速度の2乗に比例して増加します。
速く泳ぐためには?
3つの抵抗の中で、泳ぎのスピードと共に増加する幅が最も大きいのは造波抵抗です。
それに次いで大きくなるのが圧力抵抗です。
粘性抵抗は2つよりは比較的影響が少ないです。
競泳では泳ぎの技術を向上させることで、これらの抵抗と上手くつきあっていきます。
泳ぎの技術を向上させてスピードアップさせるには、次の3つのことが必要です。
✅抵抗が極力増えないようなフォームを身につける
✅水の流れ、水の抵抗を受け流せるくらい体を素早く切り替えせる(特にスプリント)
✅キックやプルのフォーム改善、パワー増加で推進力を大きくする
✅これら3つができる体を作る!
初心者さんの場合は技術的な伸びしろが膨大なので、特にこちらが中心になります。
最終的には、筋力、筋パワーの向上で泳ぐスピードが上がった分だけ増加する抵抗にある程度打ち勝ちつつ、技術的な向上で抵抗を最小限に抑えたり、受け流せるようになることです。
抵抗を生みにくい技術と抵抗に打ち勝つパワー
多かれ少なかれ、泳ぐスピードが上がるにつれ水の抵抗は増加します。
それは技術的に高いレベルに合っても、ある程度は増加してしまうものです。
水の抵抗を少なくすることはできても、ゼロにすることは不可能です。
ある程度のレベルに達した選手は抵抗に打ち勝つパワーが求められますし、
水中で体を切り返す身体能力、水の抵抗を感じる能力も求められます。
こういったスイムチューブ(↓)を使って(引っ張ってもらう)自分が出せる以上の速度で練習するのも、抵抗を感じたり、体を素早く動かしたりするため。
こうした点に関して、水中トレーニングだけで鍛えるのは難しく、陸でのトレーニングを通じて身体能力を上げていくことが絶対的に必要になります。
それもあって、私たちFORMSでは競泳スイムレッスンの初回に身体チェックや陸トレの提案を実施しています。
パーソナルトレーニング(対面・オンライン)もそのために実施しており、効果を挙げています。
水の抵抗と上手く付き合っていこう
いかがだったでしょうか?
今回は水の抵抗についてのおさらいをしてみました。皆さんがフォームを改善し、泳ぎを考える手助けになれば幸いです。
水の抵抗を減らしたり、打ち勝ったりしていくにはそれなりのフィジカルも必要です。
技術を再現するためには、それなりのフィジカルが必要です。
「泳ぎ方を知る」だけでは技術が再現できないので、水泳選手はムキムキなんです(笑)
どちらかだけでいいことはなく、「どちらも」。
【実際に僕たちが使ってて良かった&おすすめグッズ一覧】

手で水をかく動き、スイマー必須のトレーニングは懸垂!!
体を運ぶ力、手の力、全て鍛えるには懸垂が1番!!
従来の家庭用の懸垂器具は不安定感があって怖かったのですが、最近見つけたここのメーカーの懸垂器具は天井と床で突っ張るのと、絶妙に角度ついてるので超おすすめです。

あと、足首を強くする効果もあります!
他にもこんな記事があるよ!
水の抵抗を減らしたい!だけでなく、
水泳が上達するために大切な考え方やコツを書いた有料級の記事一覧はこちらから!!
【最近の記事ピックアップ】
【劇的変化】実際にクロールのプル(水のかき)が速くなった手の使い方
【完全版】実は違うかも?!「柔軟性が高い=水泳が速い」って本当?試合前のストレッチについても!
<参考文献>
・スイミングサイエンス G・ジョン・マレン 訳:黒輪篤嗣 河出書房新社 2018
・https://kotobank.jp/word/%E7%B2%98%E6%80%A7%E6%8A%B5%E6%8A%97-111694
・https://www.kodomonokagaku.com/hatena/?11ff8806a79db6d4a5acc5819cc4058d